今回は、試験の分野別科目の配分から考えてみます。
配分の目安
試験の配分
| 分野 | 問題数 | 80%ライン | |
| 権利 | 14 | 11.2問 | 宅建試験の鬼門 |
| 宅建業法 | 20 | 16問 | ここを重視するように言われています。 |
| 法令上の制限 | 8 | 6.4問 | 範囲が広く同じような用語に惑わされやすい |
| 税金、不動産価格 | 3 | 2.4問 | |
| 5問免除 | 5 | 4問 | |
| 合計 | 20 | 40問 |
こう見て、権利関係を落とす人が多いのではないでしょうか?
また業法は16点なんて楽勝だよ。という人も多いでしょう。
80%にするために数字の端数を調整すると、権利11、業法17、法令6、税金2、免除4といったあたりが目標になります。
業法偏重の嘘
さて業法です。16~17点が目標ですがこれクリアーしてる人多いんじゃないですか?
80%得点で16問です。
よく言われますね。業法は満点とるつもりで、、、
これ問題の出方が基本が8割なんですね。後の2割は意地悪問題です。
仮に基本の学習量が1だとしましょう。では後の2割を取ろうとしたら、細かいそれこそ重箱の隅をつつくような問題をクリアーしなきゃなりません。そんな細かいことをクリアーする労力は5くらいかかります。
学習量1で8割取れるのに全部取ろうとしたら6かかるんです。
こんなコスパの悪いことありますか?
17問取れればいいんですよ。時間はほかに使った方が得点はあがります。
それは80%→100%にするより60%→80%にする方がはるかに簡単なんです。理由は前者の2割は意地悪問題、後者の2割は基本問題だからです。
他の割合的にクリアーしていない部分のかさ上げを考えた方がはるかに合格に近づきます。
法令上の制限
ここを苦手にしている方が多いんじゃないですか?
でも大丈夫5→6にするくらいなら割合と簡単です。
問題の読み方で1問くらいは稼ぎ出すことができますので。
もちろん要件をそれなりに覚えないとなりませんが、数字がはっきり決まっているので以外にできるはずです。重要なのは問題の読み方です。
権利に深入りしない。都合よく解釈しない
権利、、、難しいですよね。面倒ですよね。できないですよね。
そこに有名講師さんの救いの言葉が下りてきます。「権利に深入りしない方がいい」
アー、一通りやったらもういいんだな。できなくても深入りしない方がいいんだからさ。業法頑張るし、、、
これが都合のいい解釈です。
何処の講師ができなくてもいいなんて言ってますか?基本と過去問くらいはできるようにしてくださいね。と言ってないですか?2割の意地悪問題を追いかける必要はないと言ってるにすぎません。
ここが宅建を何度も落とす人の大きな原因になっています。
5問しか取れませんでした。自己採点36点でした。ボーダーで発表まで落ち着いてられません。何とか36点が合格ラインでありますように、、、
人により不得意分野は違いますが、これを毎年繰り返す羽目になるのはこの苦手な部分を都合よく解釈し放置するからに他なりません。
苦手分野の30%正答を60%70%正答にする事が合格の近道ですし、業法に偏重するよりその方が簡単です。最も業法が大事なのも変わりませんが、、、
多くの人が苦しむ権利科目
言い換えれば、ほかの科目はみなほどほど取れてしまうので基準点が上がるだけ。権利の出来具合が合否に直結しています。
まとめ
権利以外の科目は70%~80%取れているなら、権利以外は合格ラインに乗っています。
伸ばすべきは権利です。
もちろん各自苦手な科目があるなら権利をその苦手な科目に言い換えてみてください。
何をどれだけ伸ばさなきゃならないか見えてきたのではないですか?
この具体的にどれだけというのが大事です。
苦手科目を放置するから特定の科目をどれだけがわからずに際限なくやり続けなきゃならない事になるのです。
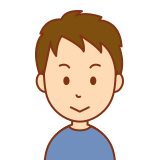
少しきつめの表現になりましたが、耳障りのいい、よく言われている事は疑った方がいいです。
今回はここまで。ありがとうございました。
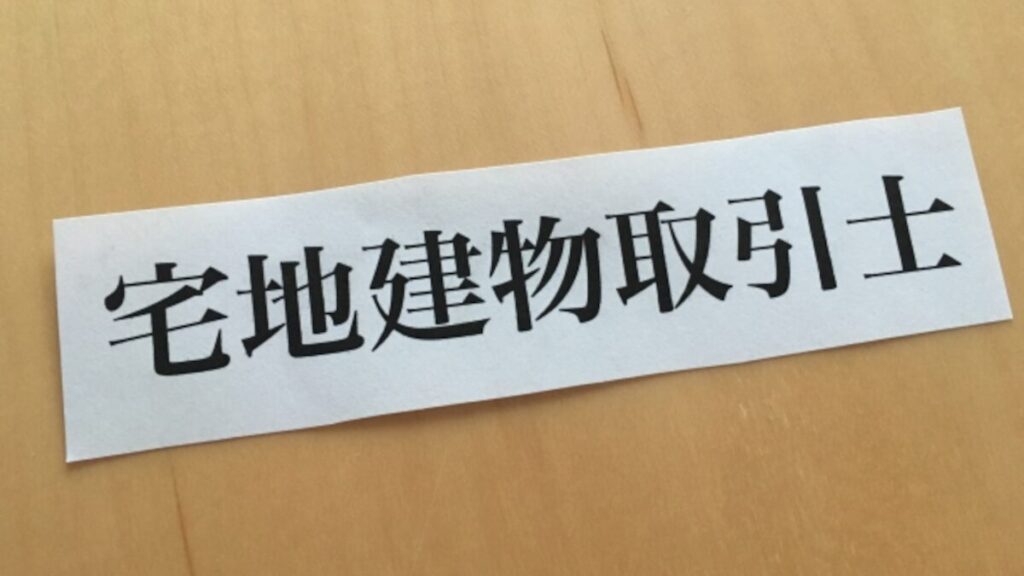
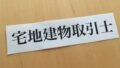

コメント